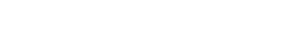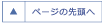- TOP>コラム
歳を重ねるごとに増加する高血圧の理解と対策
高血圧とは?
高血圧は、収縮期血圧または拡張期血圧が基準値を超えた状態を指します。
診断基準
- 収縮期血圧(上の血圧): 135mmHg以上
- 拡張期血圧(下の血圧): 85mmHg以上
どちらか一方が基準値を超えている場合でも高血圧と診断されます。
血圧の種類
- 収縮期血圧: 心臓が収縮し、動脈に血液を送り出す際の血圧。
- 拡張期血圧: 心臓が拡張し、動脈にかかる圧力が最も低くなる際の血圧。
高血圧の年齢別発生率
高血圧は加齢とともに増加します。
- 60代:
- 男性: 約6割
- 女性: 約6割
- 70代:
- 男性: 約8割
- 女性: 約7割
高血圧が引き起こす重大な病気
高血圧は、自覚症状がほとんどないため、未治療のまま進行しやすい疾患です。しかし、以下の重大な病気の発症リスクを高めます:
脳卒中
- 脳梗塞や脳動脈瘤の破裂のリスクが約3倍に上昇。
心疾患
- 心筋梗塞のリスクが増加。突然発症し命に関わる可能性があります。
慢性腎不全
- 血圧の持続的な上昇により、腎臓の機能が徐々に低下。
認知症
- 血管のダメージにより、血管性認知症やアルツハイマー型認知症の発症リスクが高まる。
高血圧予防と治療の重要性
血圧コントロールの必要性
- 高血圧は、生活習慣を改善し、血圧を適正値に保つことで、上記の疾患を予防することができます。
- 定期的な血圧測定を行い、異常があれば早期に対応することが重要です。
予防と改善方法
- 生活習慣の改善
- 塩分摂取量を控える(1日6g未満を目標)。
- バランスの取れた食事(DASH食: 野菜、果物、乳製品を多く含む)。
- 適度な運動(有酸素運動を週3~5日、1回30分程度)。
- 禁煙・節酒。
- ストレスの管理。
- 薬物治療
- 血圧をコントロールするための降圧薬を適切に使用(医師の指示の下)。
- 薬物治療を続けることで、心血管イベントの発生率を大幅に低下させることができます。
まとめ
高血圧は、加齢に伴い発生率が高まる一方で、自覚症状がないため放置されがちです。しかし、適切な管理を行うことで、脳卒中や心筋梗塞などの命に関わる疾患を予防することが可能です。日頃の生活習慣の見直しと定期的な血圧チェックを心がけ、健康的な生活を送りましょう。